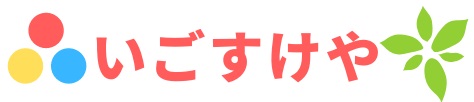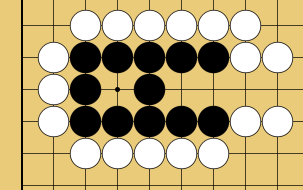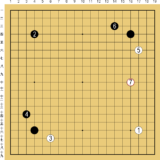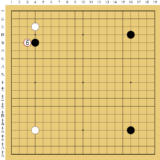目次
問題図
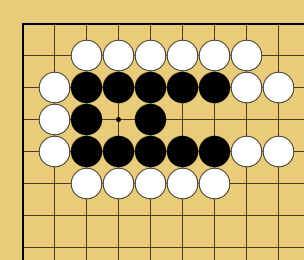
この形で黒番です。
二眼を作って生きるにはどこに打ちますか?
正解図
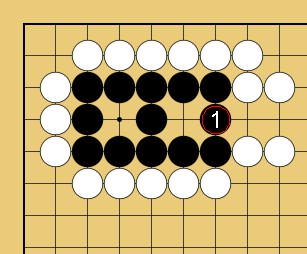
黒1が正解です。
ここに打つ事で、
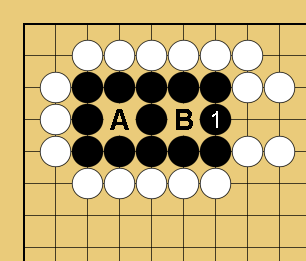
AとBに眼ができて、黒は取られなくなりますね。
白がAにもBにも入れませんので、黒は生きています。
もしも白番だったら…
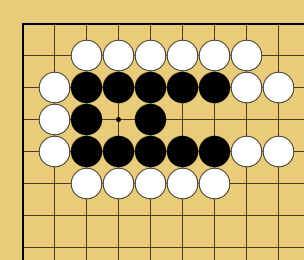
問題図の時に、もしも白番だった場合は、
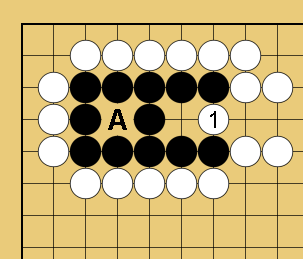
白1が良い手ですね。
ここに打つ事で、Aにしか眼ができなくなり黒一団は「死に石」になります。
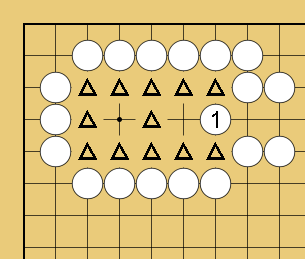
陣地を数えるときに、このようにそのまま「アゲハマ」になるのですね。
黒番であっても、白番であっても、1の場所が急所という話でした。
失敗図

黒番で黒1と打つのは失敗です。
ここに打つと、
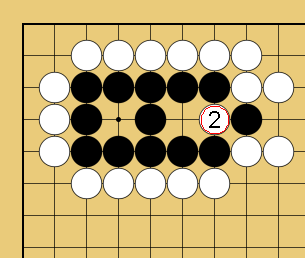
白2と「ホウリコミ」を打たれてしまいます。
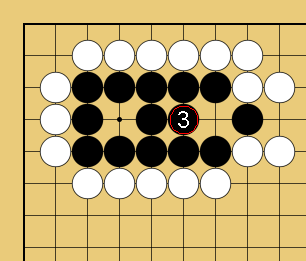
黒3と打てば白一子を取れますが、
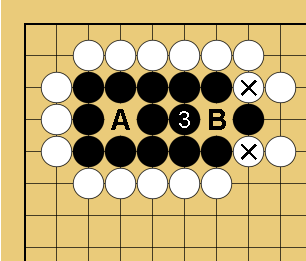
この状況は、Bの場所が「欠け眼」です。
白×によって、右側の黒一子が孤立してしまっているのです。
黒はAの一眼しかないので「死に石」になります。
Bが欠け眼であることの証明としては、
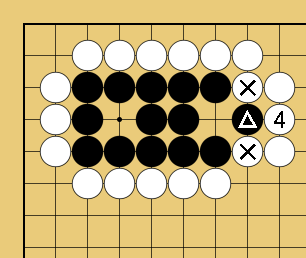
白4と打たれると、黒△がアタリですね。
白×と白4によって、アタリにされているのです。
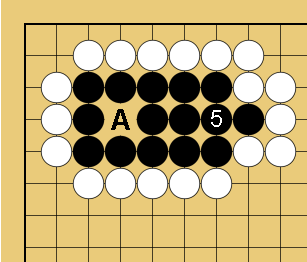
黒5とつなぎますが、この作業で黒の眼が石で埋まってしまいました。
やはり、Aの一眼しか残りませんね。
ということで、
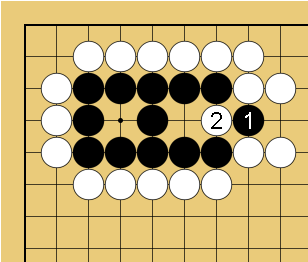
黒1と打つと、白2に打たれて黒は失敗なのです。
実戦では、お互いにこのままの形で放っておいて(黒はあきらめて)、終局になったときに、
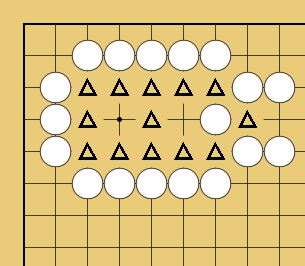
このように、そのまま黒石を取り上げて「アゲハマ」になります。
取ったあとのエリアも、すべて白地になるのです。
黒としてはこういった状況にならないようにしたいですね。
ですので、
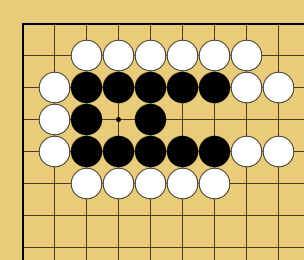
問題図の時に、
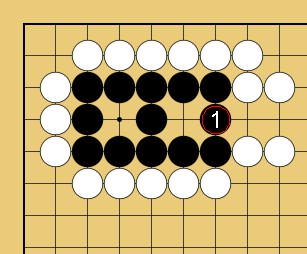
黒1は大事な一手ですね。
これならば、黒は取られることなく、
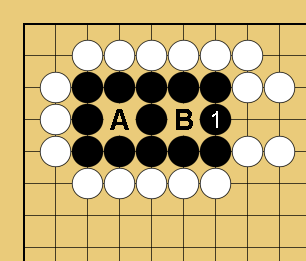
AとBが黒の陣地になります。
眼の仕組み
眼の仕組みとしては、
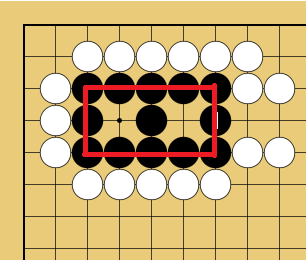
このように、黒石が縦横の線でしっかりとつながっていることがポイントです。
つながっていれば、囲まれてもアタリにされないのですね。
また、
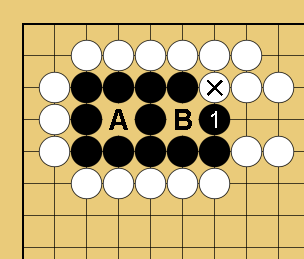
白×のように一ヵ所が欠けていても大丈夫で、Bはちゃんとした「眼」です。
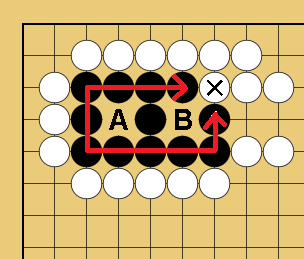
こういう風に全体が、縦横の線でつながっているのですね。
白に囲まれても「アタリ」にされないということを確認してみて下さい。
しかし、さらに、
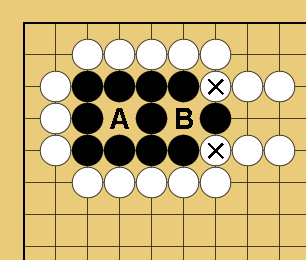
白×が増えると、Bの場所は欠け眼になります。
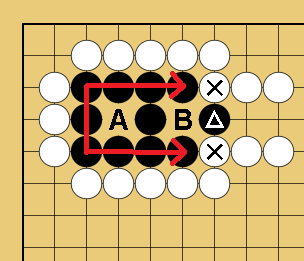
黒石のつながりがこのようになって、黒△が孤立してしまっているからですね。(白に囲まれると、黒△がアタリになってしまうことを確認してみて下さい。)
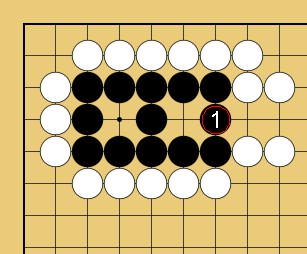
このように、黒石が縦横でつながっているということが重要でした。
OKでしょうか。
「欠け眼」に慣れることはとても大事ですので、是非、この解説をまた復習してみて下さい。
では、次は「13路盤の打ち方」を見ていきましょう。