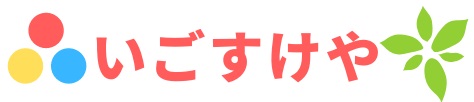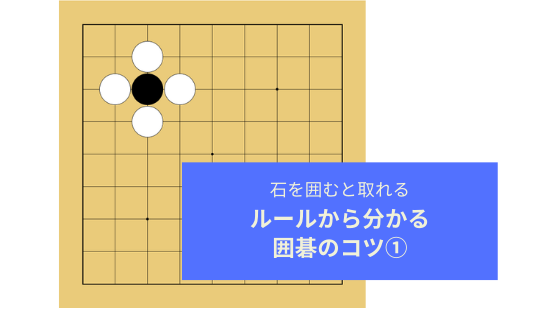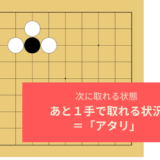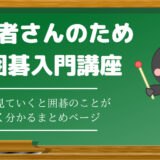囲碁の「石から出ている線を全て囲むと取れる」というルールから分かることは、「碁盤の隅の石は取りやすく、中央の石は取りづらい」ということです。
これは、初心者から高段者まで全員に共通の「囲碁のコツ」ですので、是非、本記事の解説をゆっくり見ていってください。
本サイト(いごすけや)では、囲碁のルールとやり方を学ぶ囲碁入門講座を無料提供しています。
メールアドレスだけで簡単に参加できますので、どうぞお気軽にご活用ください!
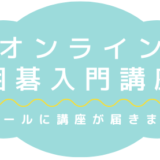 【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室
【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室 「石を囲むと取れる」というルール
まずは、「石を囲んで取る」ということに慣れていきましょう!
石を取れるという重要なルールの確認とあわせて、石を囲む練習もしっかりしておくと、なぜ隅で石を取りやすいのかが自然と分かってきます。
「囲碁の4つの基本ルール」についてはこちら:
 【囲碁入門①】難しいルールを簡単に解説!初心者向けに4つのルールをまとめた
【囲碁入門①】難しいルールを簡単に解説!初心者向けに4つのルールをまとめた
①囲むと石を取れる
まずは、簡単なルールの確認からです。
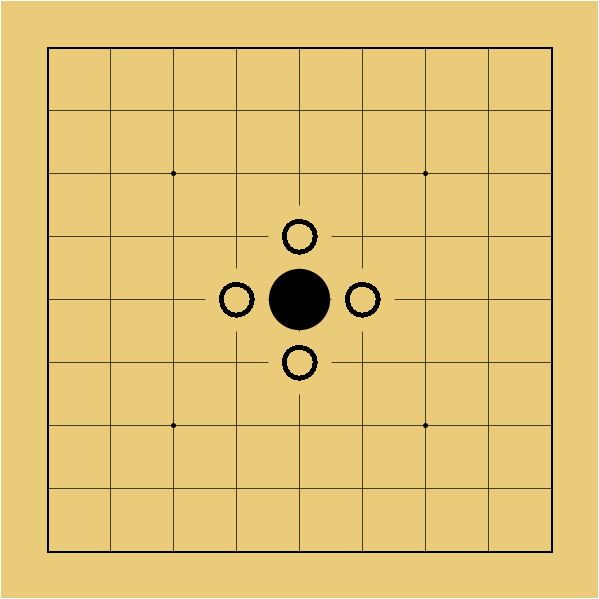
このように黒石が打ってあったとすると
〇印のように、石から道が出ています。
これを
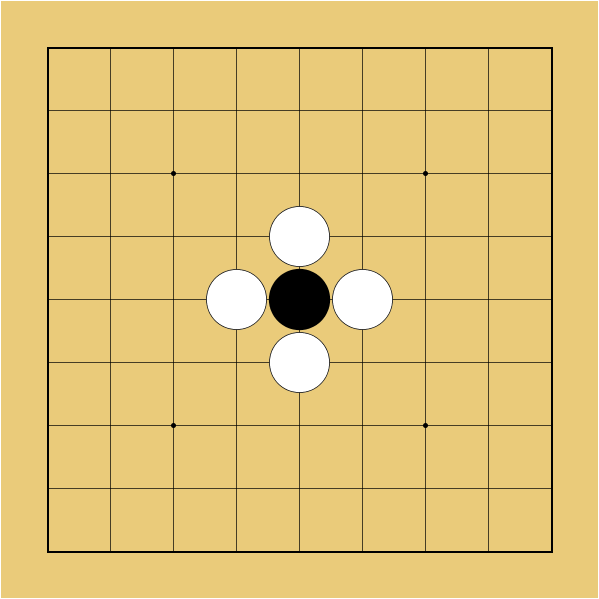
白が全てふさぐと
こんな風に白が黒を囲むと

黒を取れます。
盤上からいなくなるのですね。
これが「石を囲むと取れる」というルールです。
②囲んで取る練習
では、白石を使って、黒石を囲んで取る練習をしましょう。
碁盤をお持ちの場合は、是非碁盤に碁石を並べて一緒にやってみましょう!
石を囲んで取る練習(1)
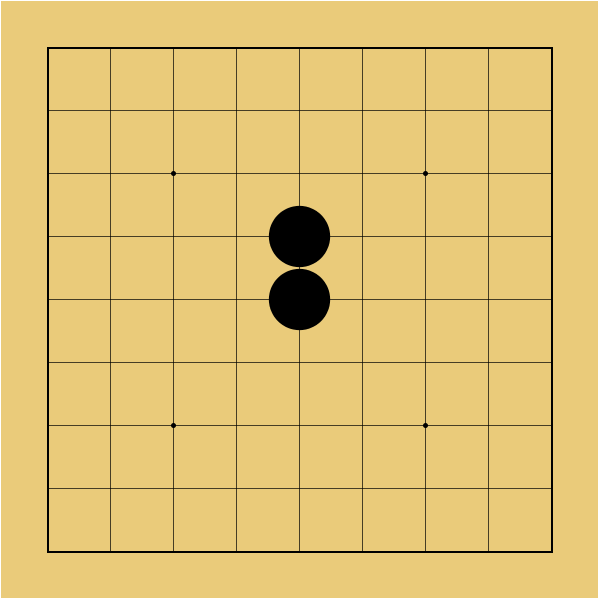
この黒はどうでしょう?
この黒2子を取るには…?
白をどのように配置すれば良いでしょうか。
黒から出ている道を確認しましょう。
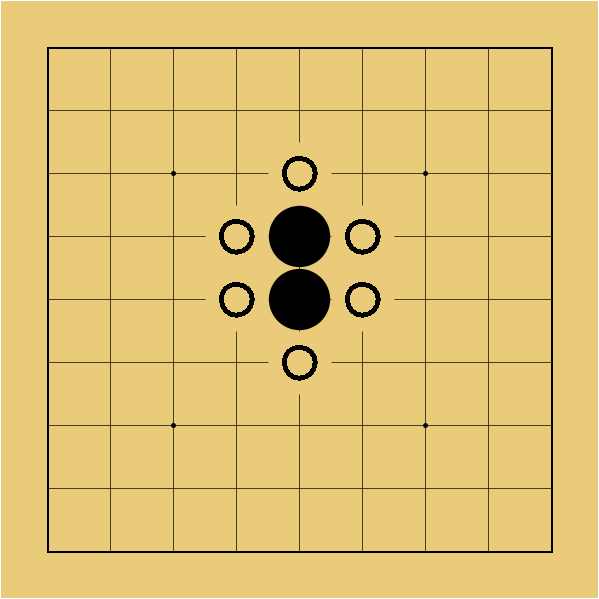
黒からは、この〇印のように道が出ています。
これらを

白が囲むと
黒を取れます。
この際、△の場所に白石は不要です。
黒から線が出ていませんから。
斜めは囲む必要がないのです。
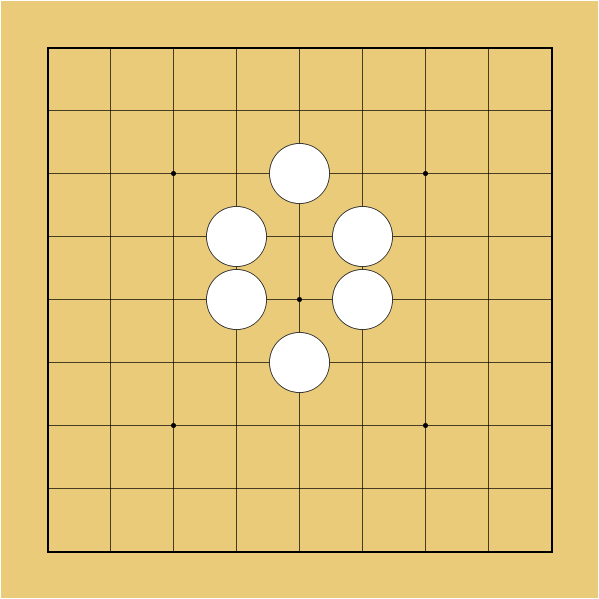
このように黒石がいなくなりますね。
では、もう一ついきましょう。
石を囲んで取る練習(2)
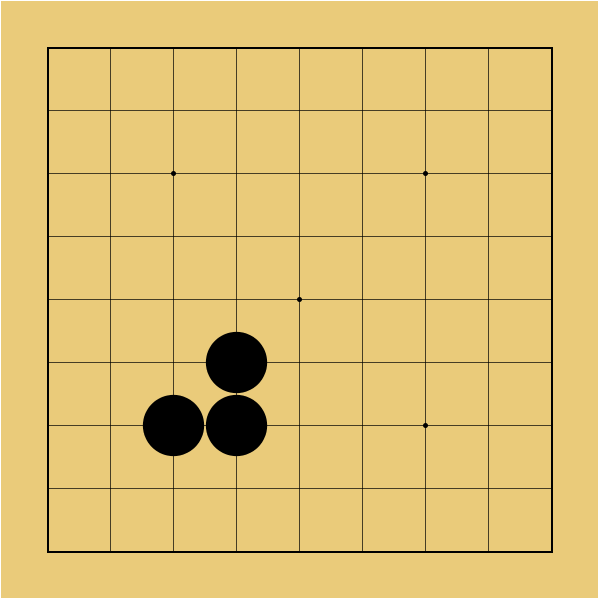
この黒石を取るには?
石が増えましたが
石から出ている道を見極めて…
考えて下さいね。
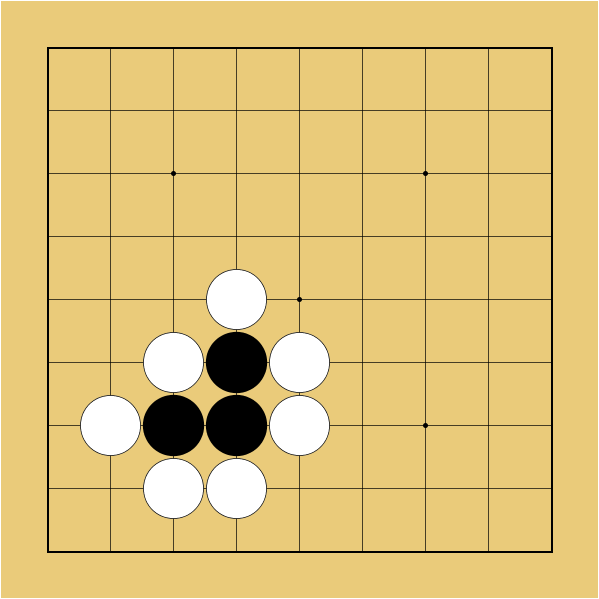
こうです。
合ってましたか?
黒石から出ている、全部の道をふさいでいます。
このように石数が多くなっても
道をすべてふさげば取る事ができます。
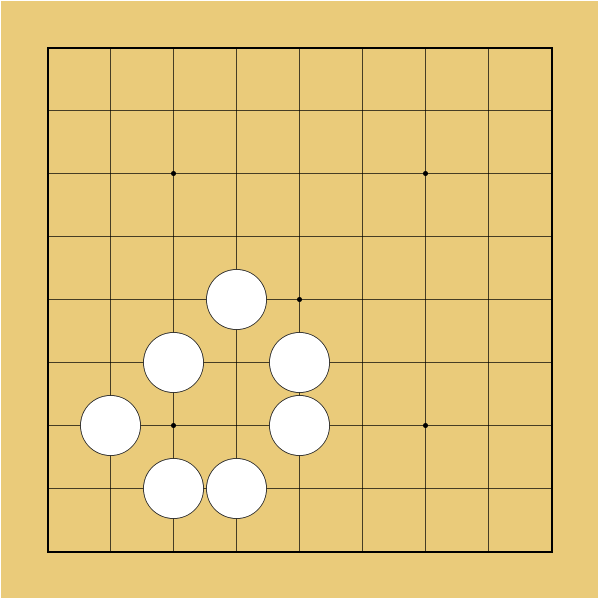
このようになりますね。
次も行きましょう。
石を囲んで取る練習(3)
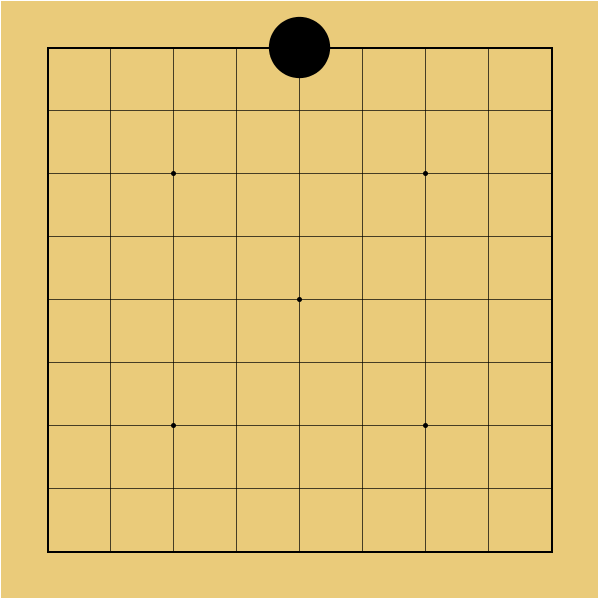
この黒を取るには…?
黒石から出ている道を確認しましょう。
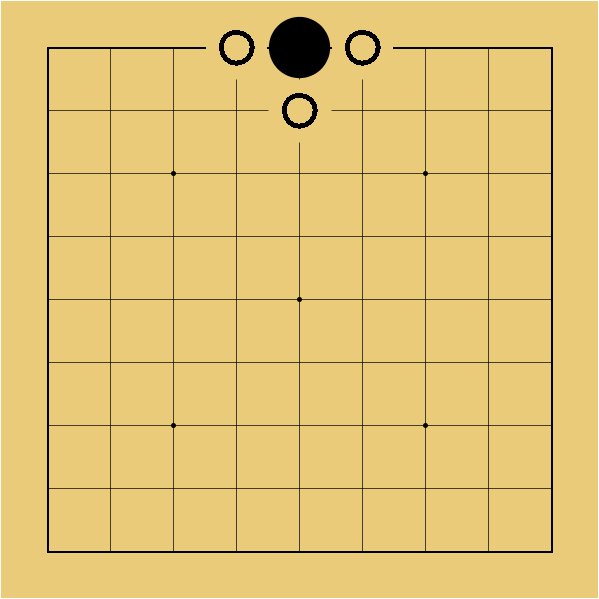
この〇印ですね。
端っこは線がないので不要です。
というよりか置けませんね。
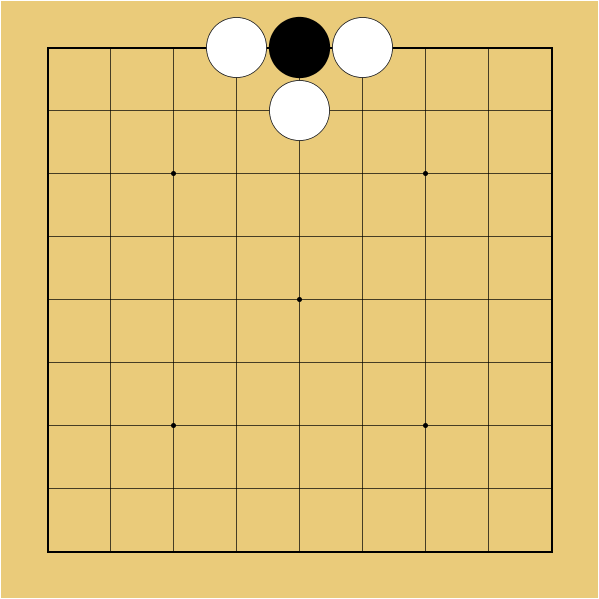
これで取れます。
では、これは?
石を囲んで取る練習(4)
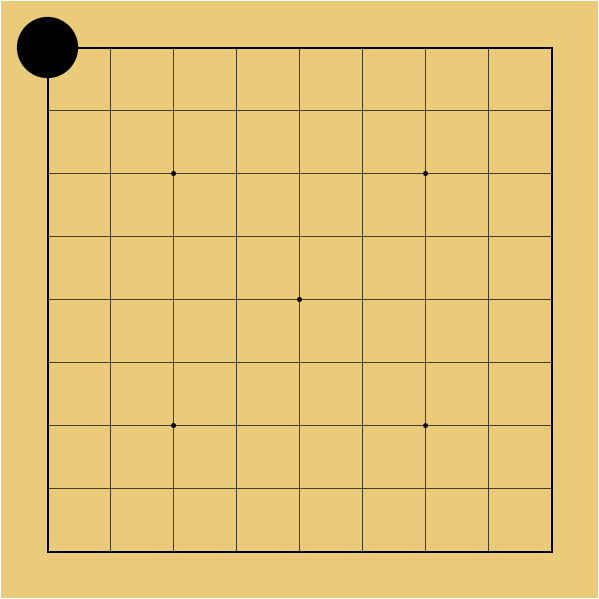
同じ要領で
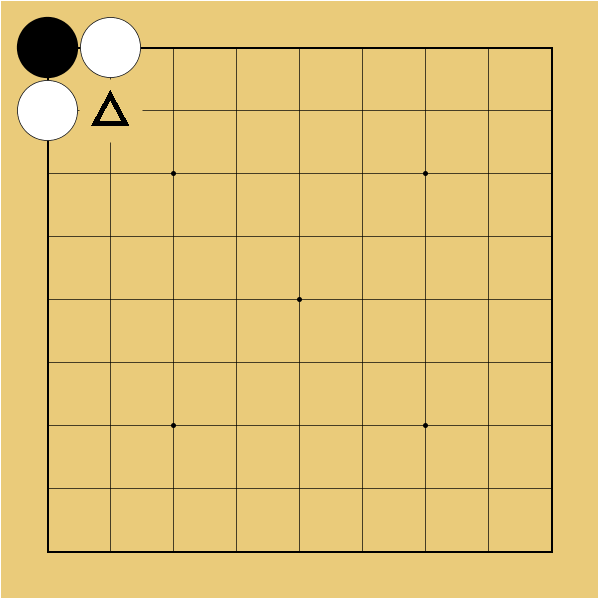
こうですね。
△の場所は道がないので、白石は不要です。
…最後の2問で一つの法則が分かります。
ルールから分かること
下の図を見てみて下さい。
黒1子の取り方についてなわけですが
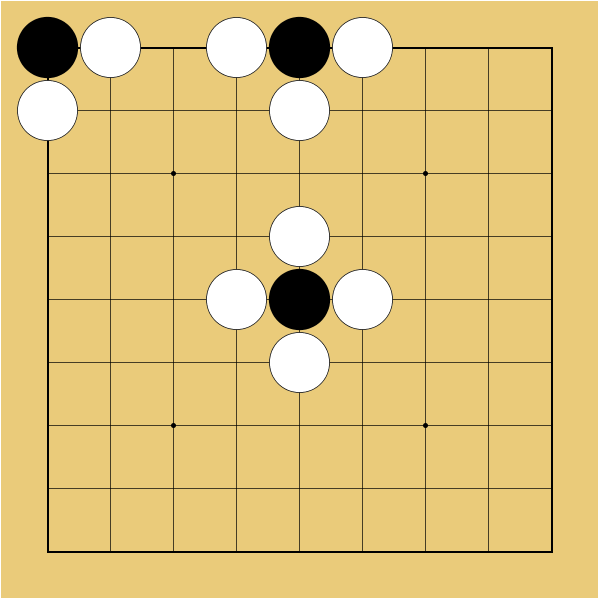
どれも黒を1子取っている状態です。
しかし、違いがありますね。
しかも2つ。
一つは
「石の数」ですね。
黒を取るまでにかかる石の数が違います。
もう一つは
「場所」です。
中央、辺、隅の3か所です。
辺(へん)というのは
端っこと端っこの間のエリアのことです。
それで、結局
「場所によって取るためにかかる石数が違う」
ということです。
そして
「隅に行けば行くほど取りやすい」
「中央の石ほど取りづらい」
という法則があるのです。
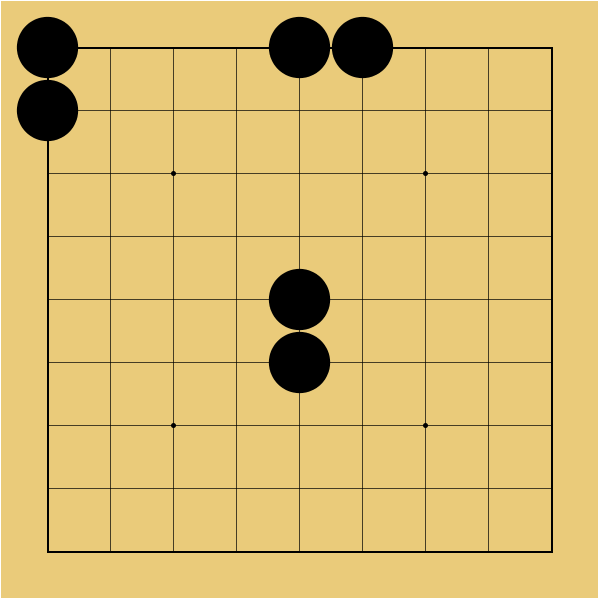
この法則は
石数が増えても当てはまります。
練習もかねて、
上の図の各黒2子を白で囲んでください。
想像しました?
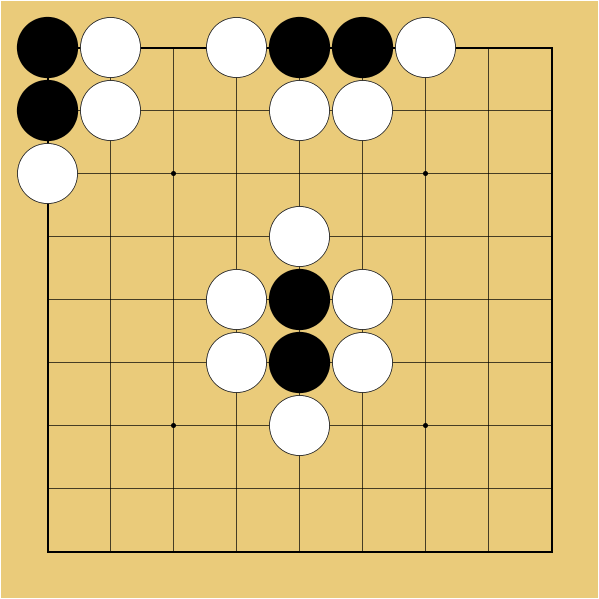
こうですね。
そして
中央の黒を取るために⇒白6子
辺の黒を取るために⇒白4子
隅の黒を取るために⇒白3子
と、場所によってかかる石数が違うのでした。
「隅の石は取りやすい」逆に言うと
「隅の石は取られやすい」ですね。
これが、囲碁の最大のコツの一つです。
まとめ
- 隅の石は取りやすい(取られやすい)
- 中央の石は取りづらい(取られづらい)
対局をするときには是非意識してみて下さい!
次は、「アタリ」という囲碁用語についてお話ししますね。
本サイト(いごすけや)では、囲碁のルールとやり方を学ぶ囲碁入門講座を無料提供しています。
メールアドレスだけで簡単に参加できますので、是非お気軽にご活用ください!
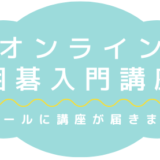 【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室
【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室 ※以下も要チェック!
いごすけやでは、囲碁入門講座以外にも級位者向け(対局経験ありの方向け)の講座も提供しています。
級位者向けの講座は、ルールを知っていることが前提で話が進んでいきますので、これから囲碁を始める方は上の「入門講座」をお受けください。
反対に、対局経験がおありの級位者の方は、以下の「初級・中級者向けの囲碁オンライン講座」が上達に役立ちます。
 【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ
【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ ※また、いごすけやの囲碁入門ではどんなことを学ぶのか?という全体像については下のまとめ記事をどうぞ。