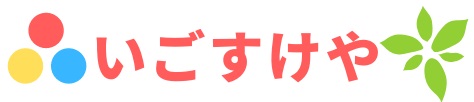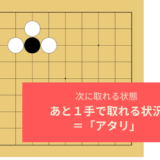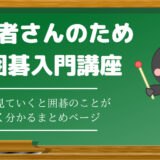今回は「欠け眼」について勉強しましょう。
この解説を読むと、「欠け眼」の基本についてよく分かり、構造が理解できます。
また、漢字は「欠け目」ではなく「欠け眼」と書きます。
欠け目は、「減量」や「不完全な部分」という意味の一般的な言葉で、欠け眼は囲碁の死活問題の専門用語なのです。
是非、「欠け眼」についてゆっくり学んでいってください!
重要項目「欠け眼」
欠け眼は「眼のようで眼でない」という紛らわしいものです。
仕組みなども含めてゆっくり見ていきましょう。
「欠け眼」とは?
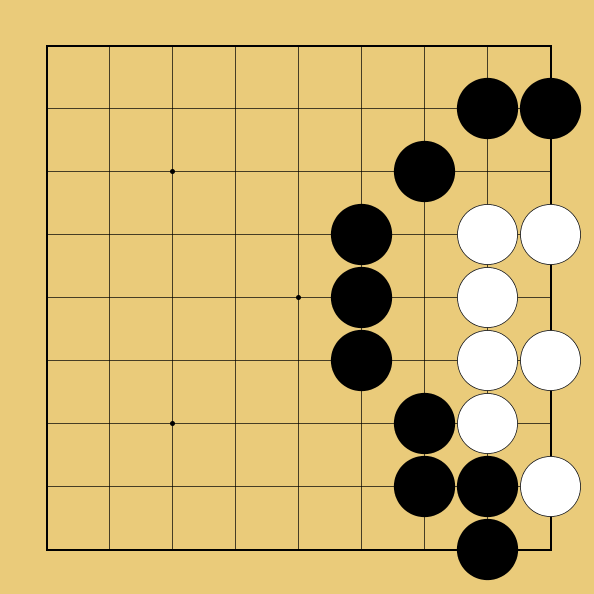
さて、今回はこのような図です。
この白はどうなっているでしょうか?
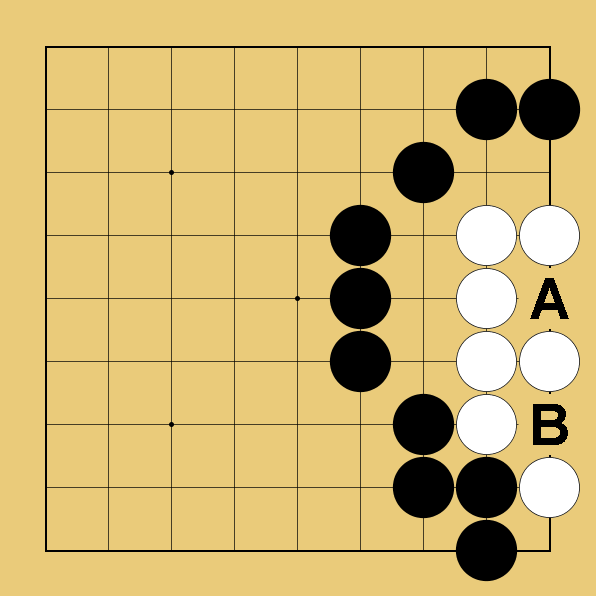
AとBで「二眼」あるようにも見えます。
しかし…
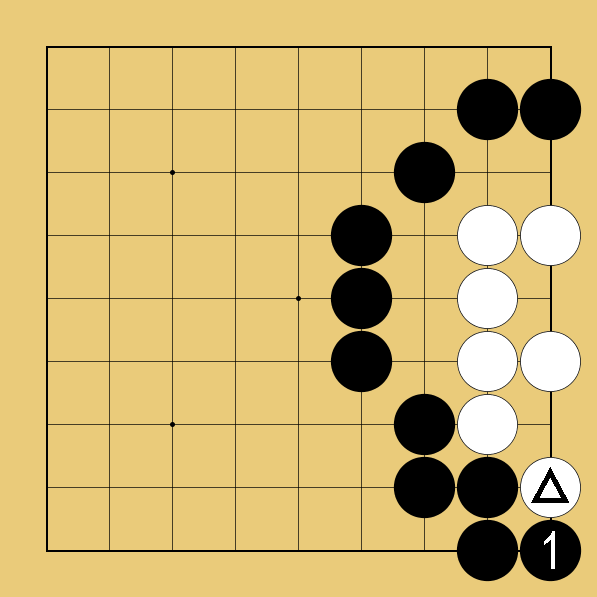
黒に1と打たれると、白△がアタリになりますね?

なので白は、取られないためには、白2とつなぐのですが…
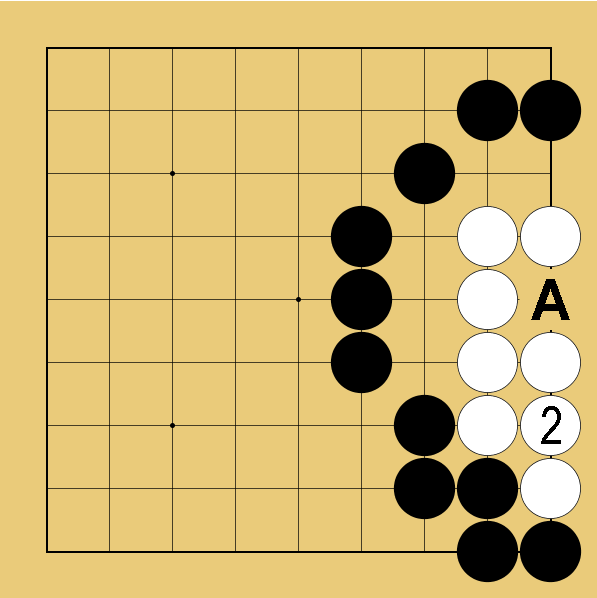
こうなると、結局白はAの一眼しかできない状況になって、「死に石」になってしまいます。
OKでしょうか。
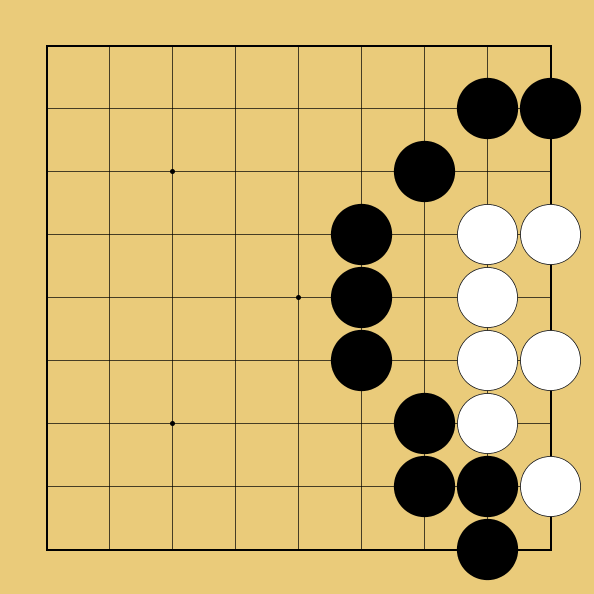
では、元の図に戻って、今度は白番で抵抗してみます。
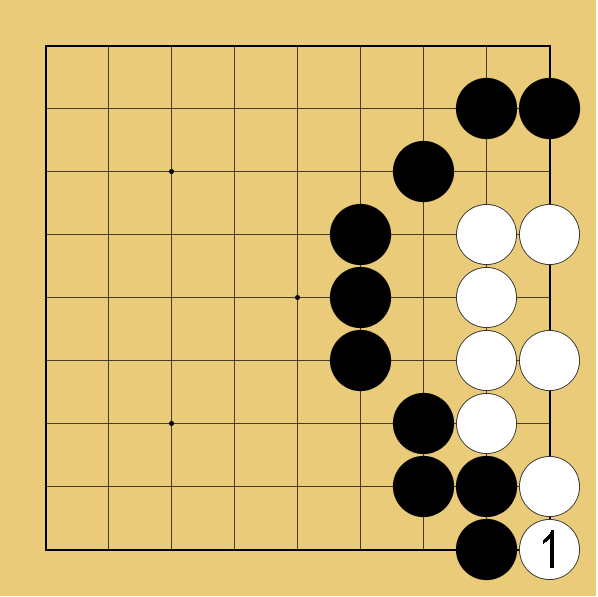
例えば、先ほど黒に打たれた場所に打ってみると、この状況は…
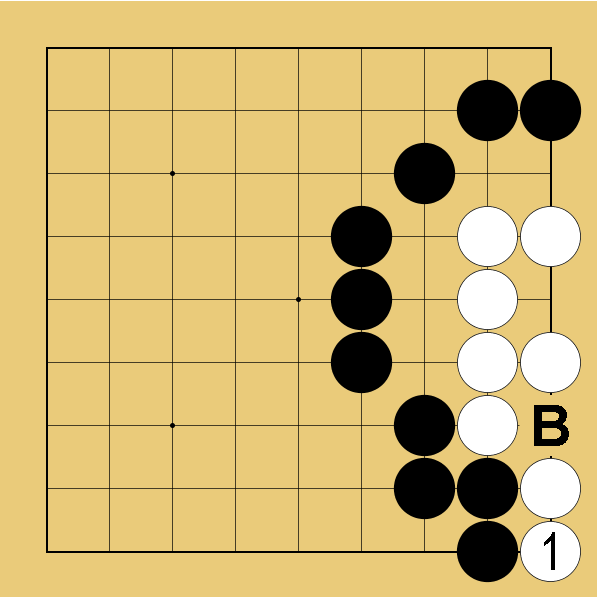
白二子がアタリですね。
黒にBと打たれると取られてしまいます。
つまり、Bの場所は白の眼とは言えないのです。
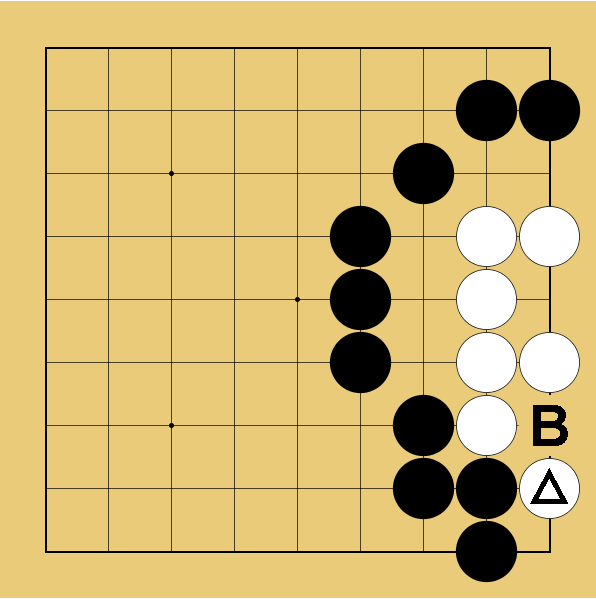
また冒頭の図に戻ります。
この状態は、Bの場所は白の眼ではありません。
黒に打たれると白△がアタリになってしまいますし、白から抵抗しても、結局アタリになってしまいます。
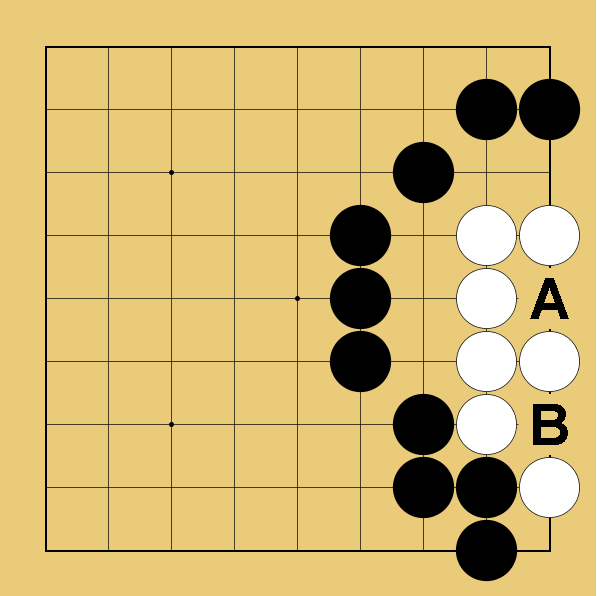
この白Bの事を「欠け眼」と言います。
Aは眼ですが、Bは欠け眼です。
なので、この白は「一眼で死に」の状態です。
終局して、陣地を数える時に「アゲハマ」になる石なのですね。
欠け眼の原理
白Bの場所は何が欠けているのか?
という話になってきます。
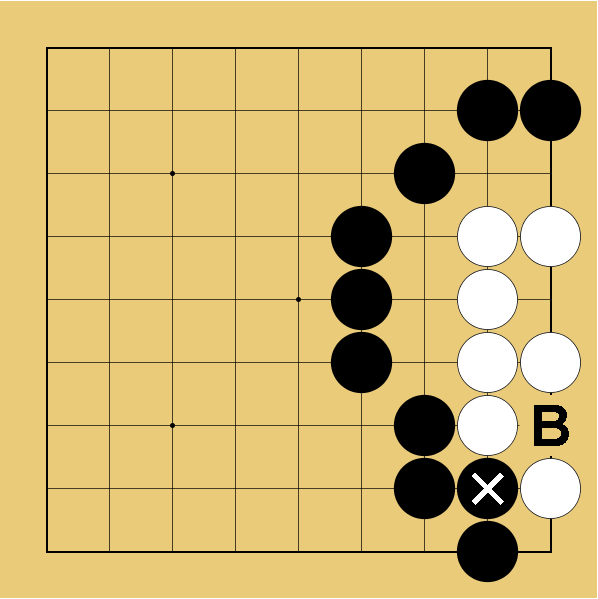
ポイントは黒×の存在です。
ここが、白Bが眼として欠けている点なのです。
ここが非常に解りづらいところなのですが、
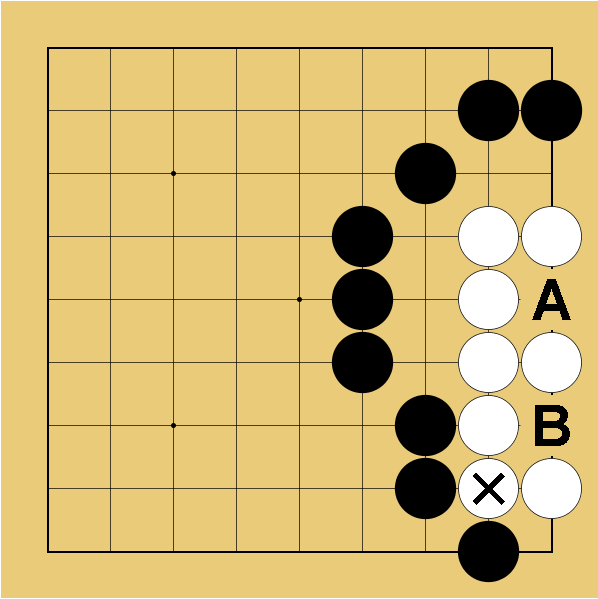
もしも、×の場所が白だったら、Bは白の眼になります。
白石が縦横でしっかりつながっているところがポイントです。
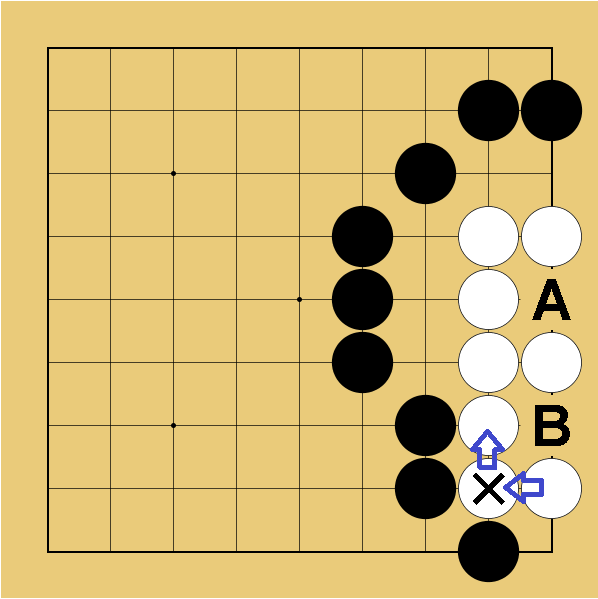
こんなイメージです。
白×によって、角が欠けることなくつながっています。
そうすると…
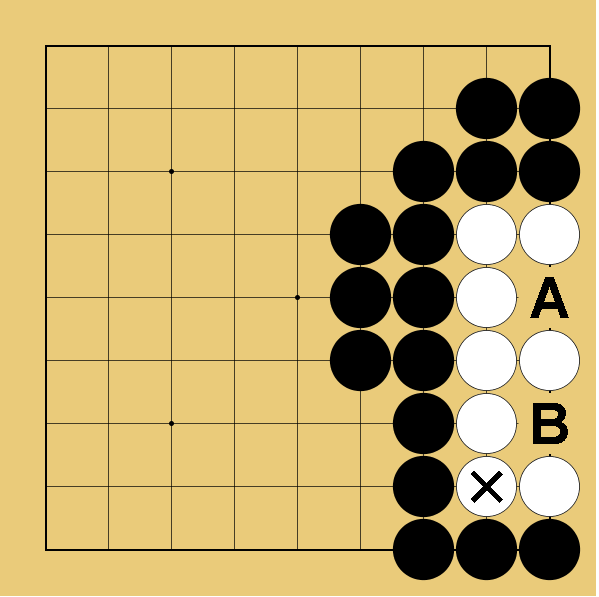
周囲を黒に埋め尽くされても、白はアタリになる事がありません。
AとBの二か所が空いています(二眼)。
でも、白×が黒だったら、
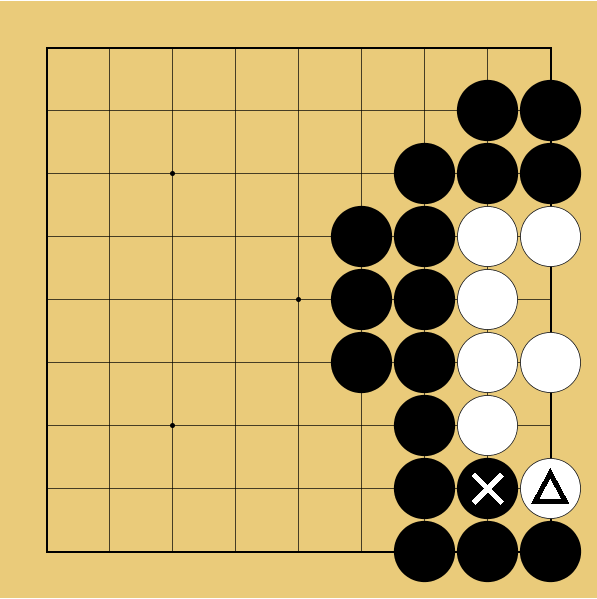
白△がアタリになってしまいます。
これが「欠け眼」ですね。
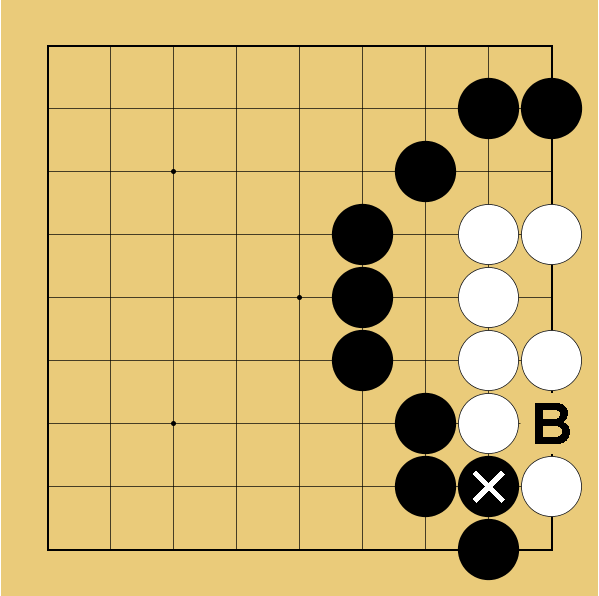
周りが黒で埋まっていなくても、×の場所が黒ならば、Bは「欠け眼」なのです。
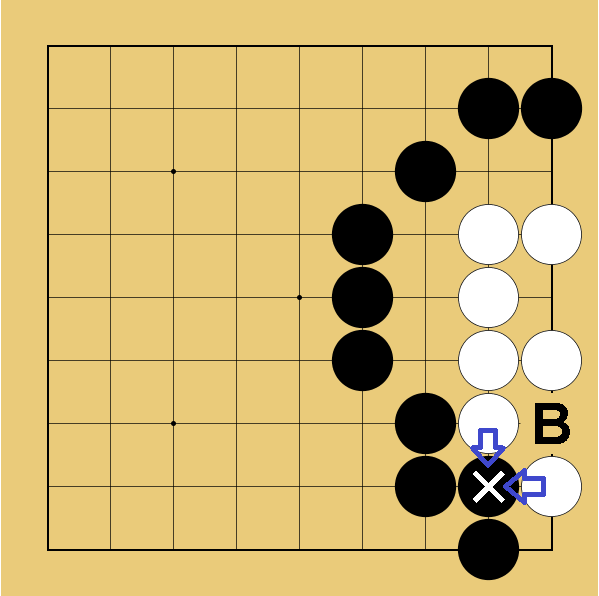
黒×が白石のつながりをジャマしているのですね。
ということで、
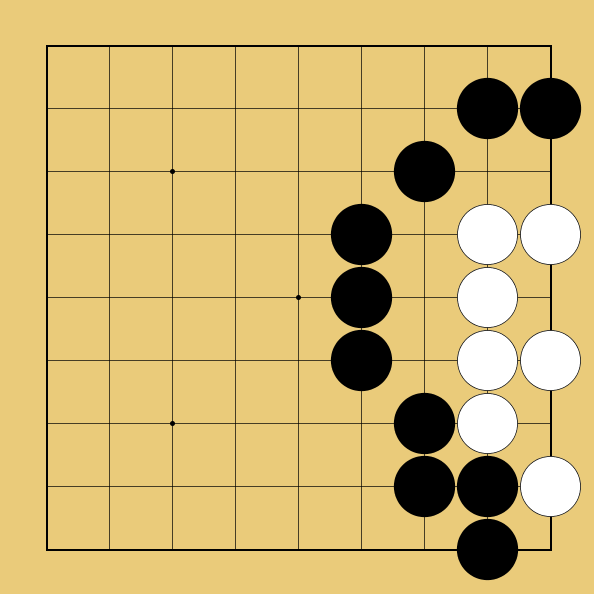
最初のこの図は、白は二眼あるとは言えず「死んでいる状態」です。
一眼しかないのです。
どうでしょうか。
ここが囲碁の入門で最もつまづきやすいところです。
ということで今度は、死活の重要ポイント「欠け眼」を見極める練習をしたいと思います。
何度も見ることで、欠け眼についてよく分かってきます。
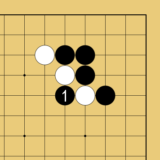 【囲碁の練習問題】習うより慣れる!初級手筋・死活問題をプレゼント
【囲碁の練習問題】習うより慣れる!初級手筋・死活問題をプレゼント
欠け眼の練習問題
死活判断の練習①
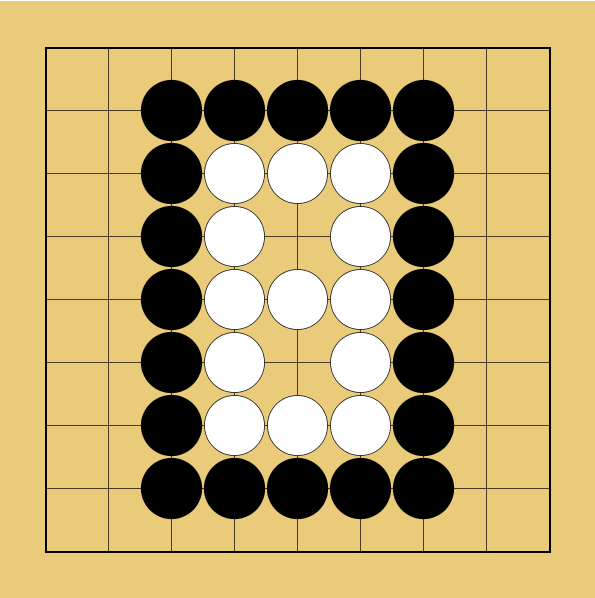
この図から順を追って解説していきます。
この白は…
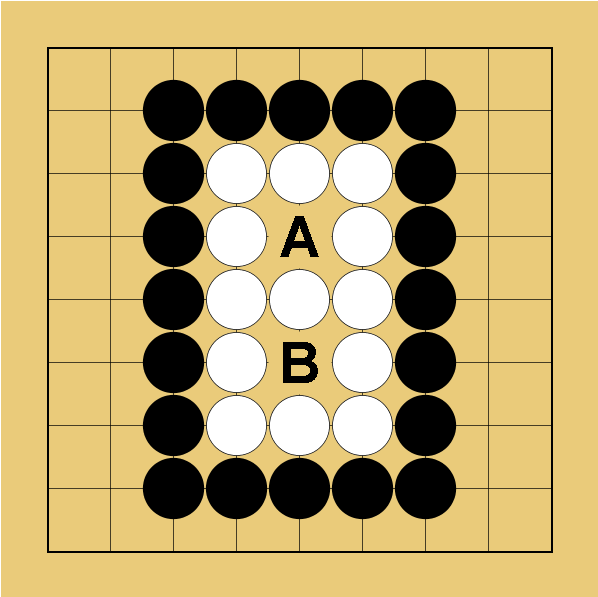
AとBの二眼で生きています。
OKですね。
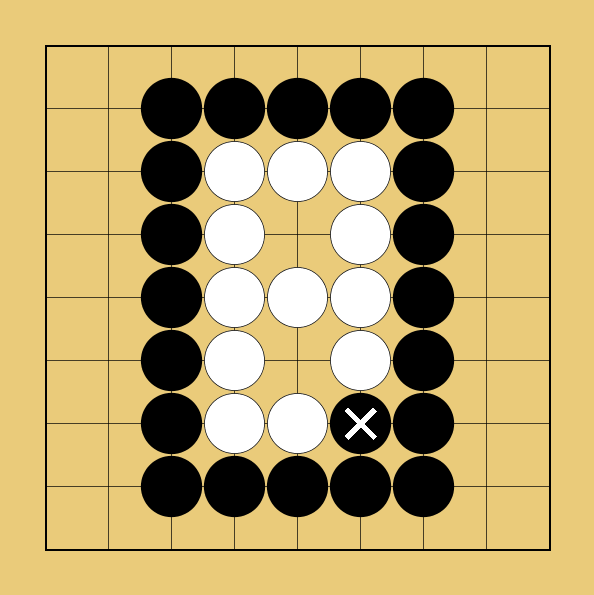
では、この図はどうでしょうか?
黒×が加わりました。
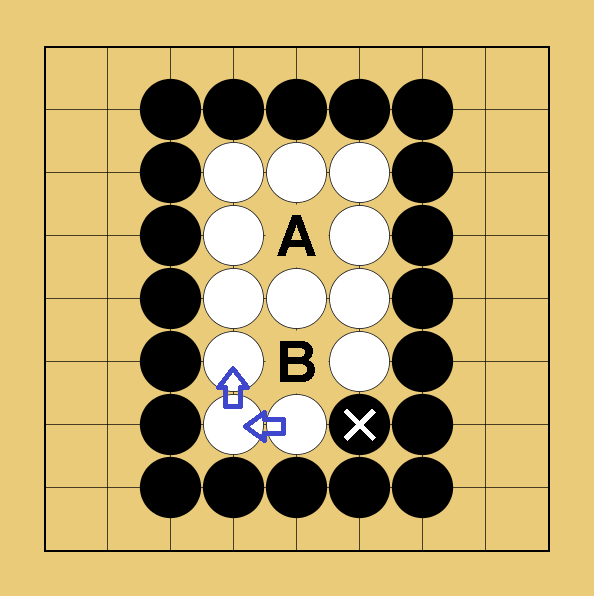
この白も、AとBは両方とも「眼」で、二眼を持って生きています。
黒×で片方の道は欠けてしまいましたが、青矢印のルートで白石がつながっています。
このように、石がしっかり線でつながりながら囲んだ陣地が「眼」になるのです。(白がアタリにならないことがポイント)
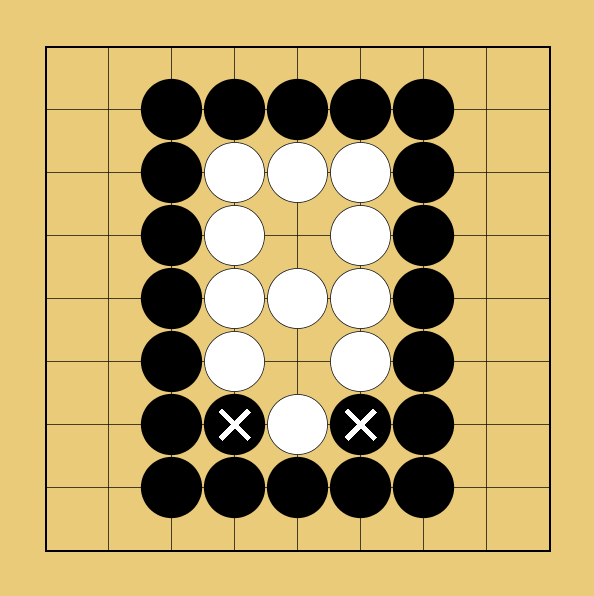
では、今度はこの図です。
黒×がさらに増えました。
どうなっているのかというと…
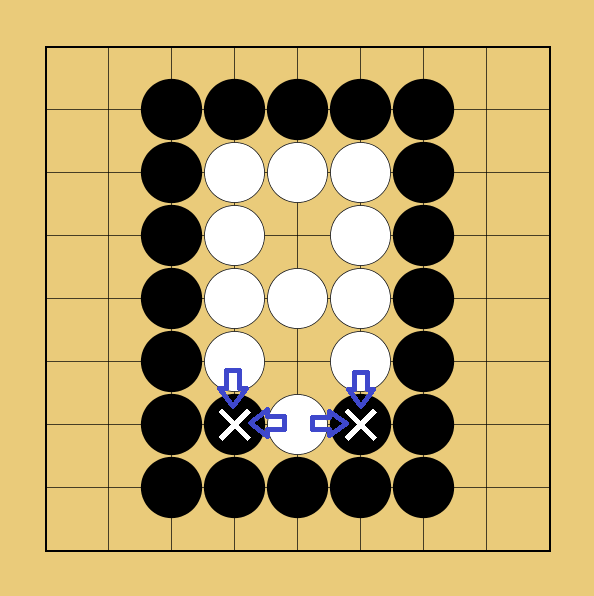
この状態は、白一子がアタリですね。
理屈としては、黒×によって白石の道をジャマされてしまっています。
だから、孤立している白一子がアタリになるのです。
そして、これが「欠け眼」ですね。
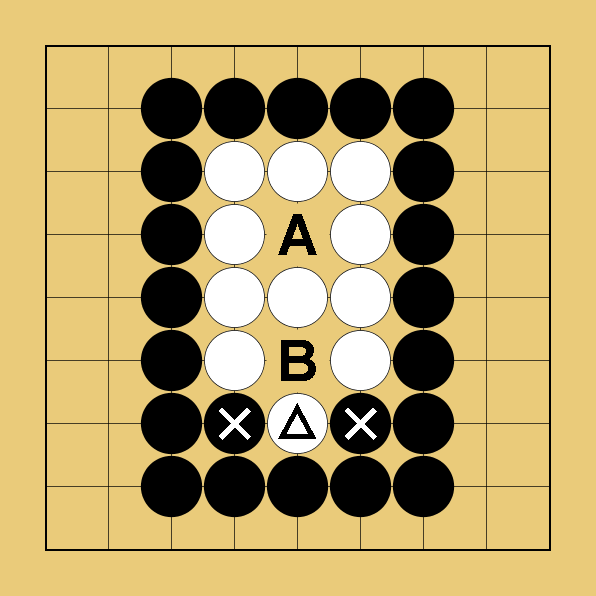
Aは白の「眼」ですが、Bは黒×たちの存在によって「欠け眼」です。
なので、この白は「一眼で死んでいる」という状態ですね。
終局して陣地を数えるときに「アゲハマ(死に石)」になります。
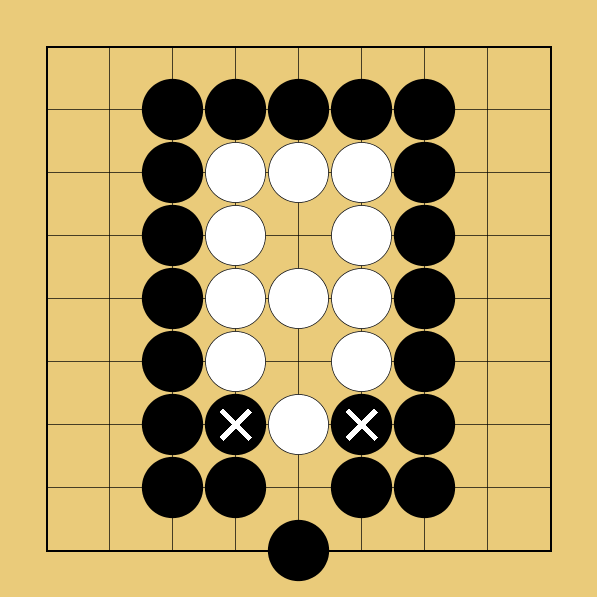
そして、黒石が少し離れたとしても、黒×がいることで白は欠け眼になります。
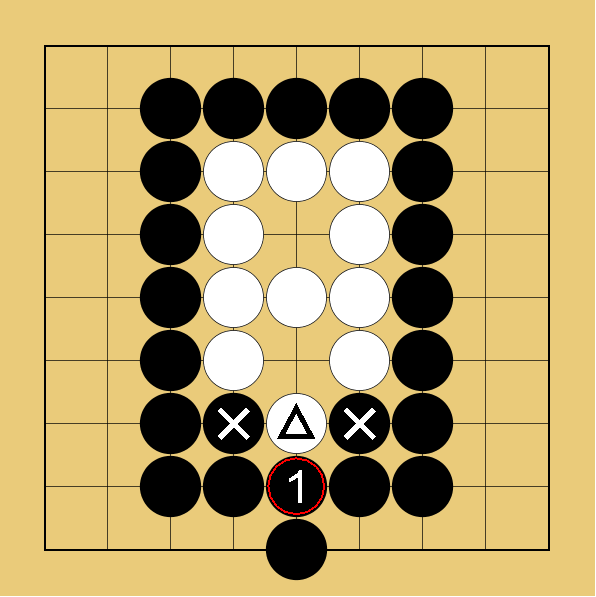
いつでも、黒が1と打てば白△がアタリになり、

白2とつないだとしても、白はAの一眼だけになって、取られてしまいます。
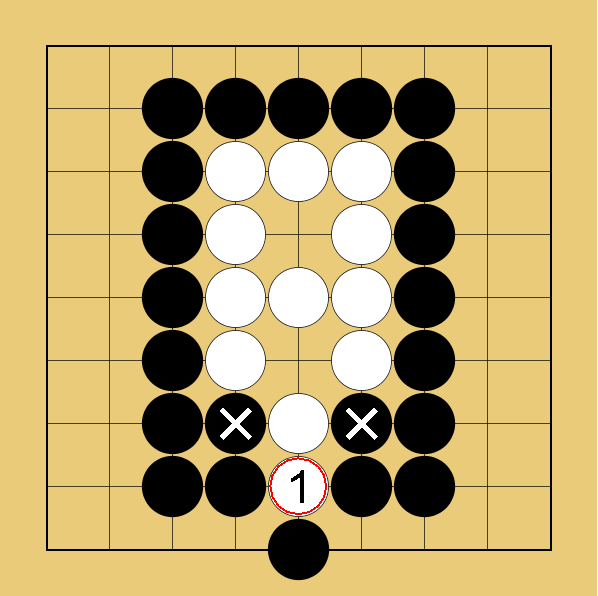
また、白番だとして1と打っても、結局白はアタリになってしまい、眼はできません。
黒×が重要なのです。
死活判断の練習②
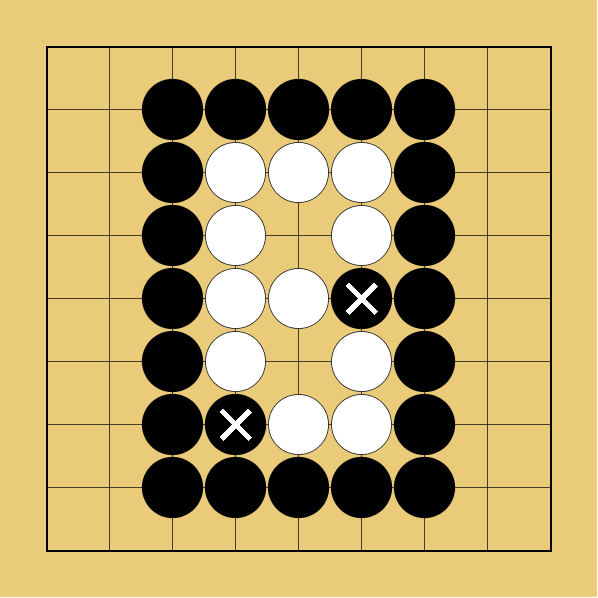
今度はこの図を見てください。
黒×の場所がこのようになりましたが、白はどうなっているでしょうか?
生きているのか、死んでいるのか…
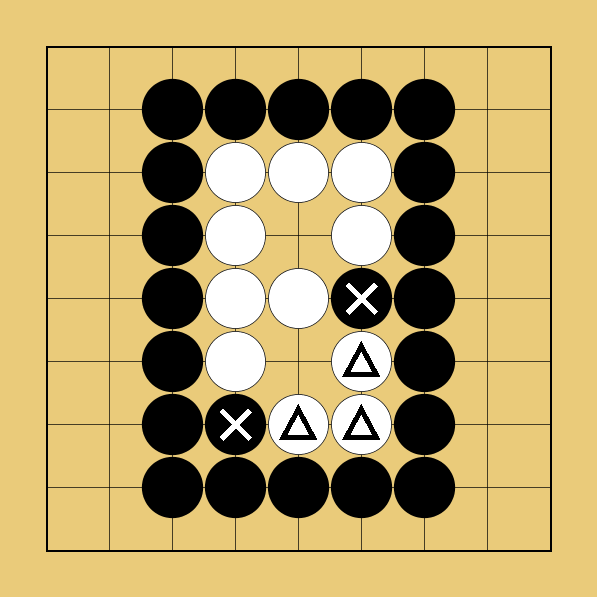
よーく見ると、白△がアタリですね。
つまり、
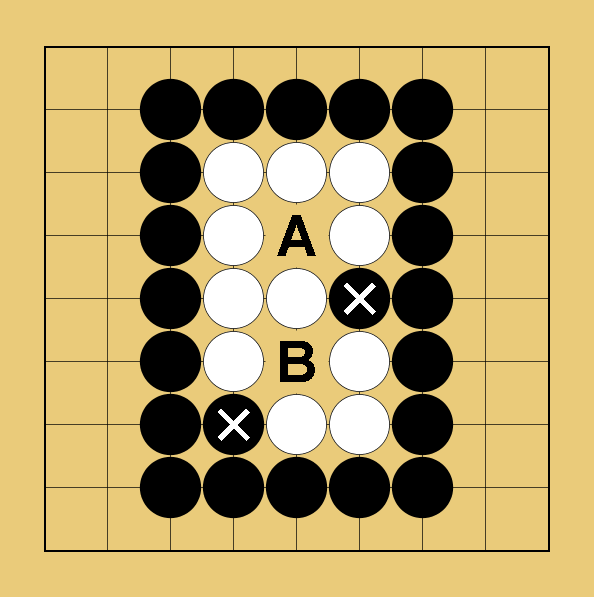
Aは白の「眼」ですが、Bは「欠け眼」ということになります。
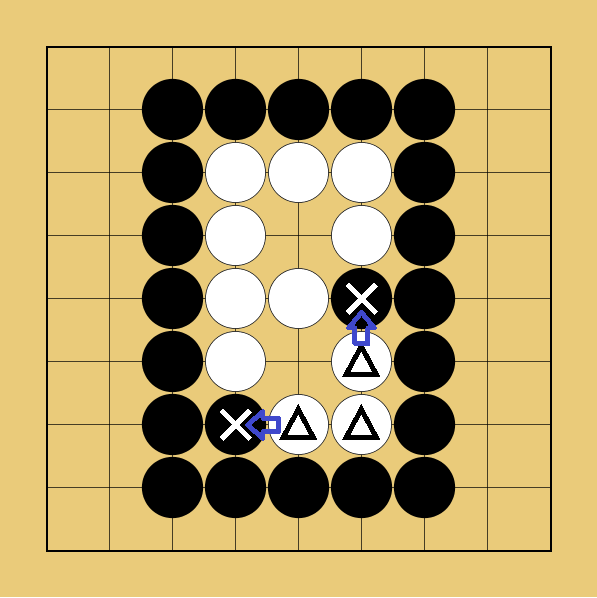
やはり黒×の存在がポイントで、白△の道をジャマしています。
このようになると、白△がアタリになることが確定するのです。
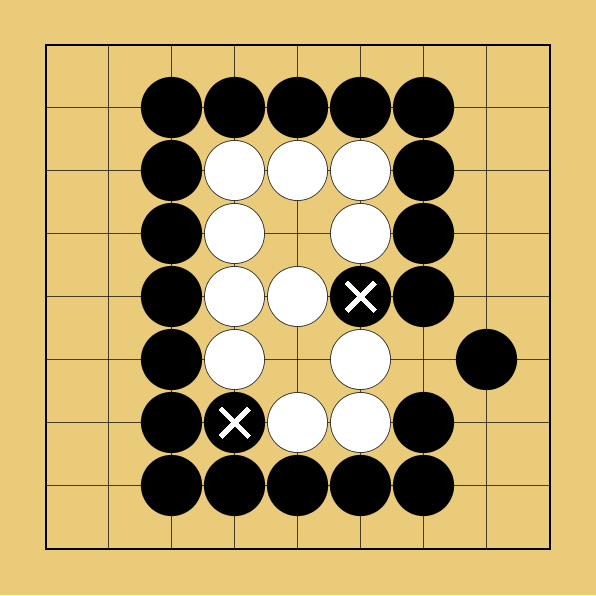
なので、黒石が少し離れていて、今アタリでなくとも…
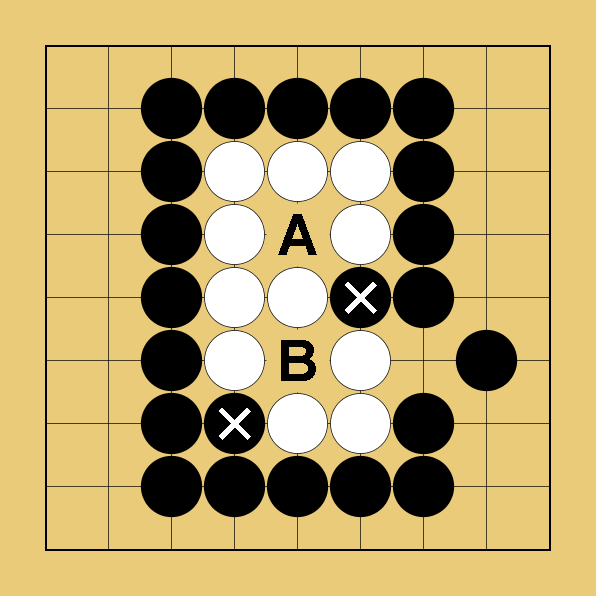
Bの場所は欠け眼なのです。
白は一眼で死んでいます。
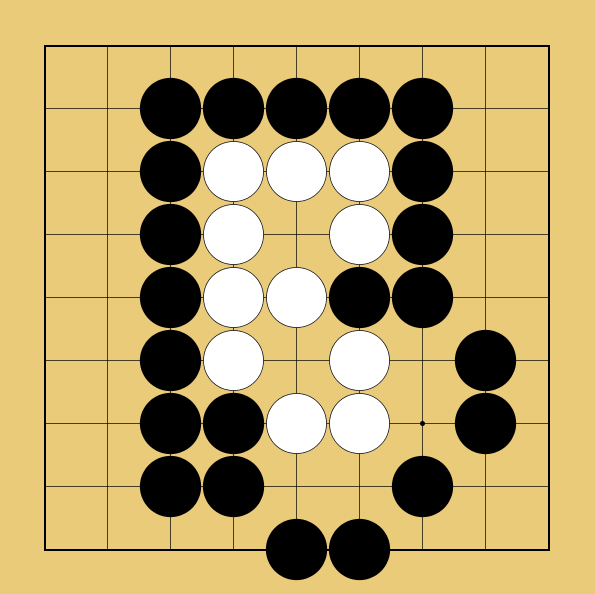
黒石がこれだけ離れていても…
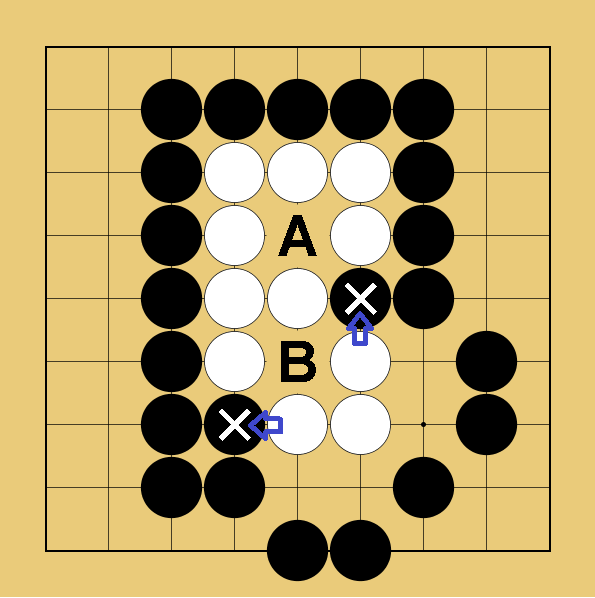
黒×がいることで、Bの場所は欠け眼になります。
白の道をジャマしているのですね。
死活の判断練習③
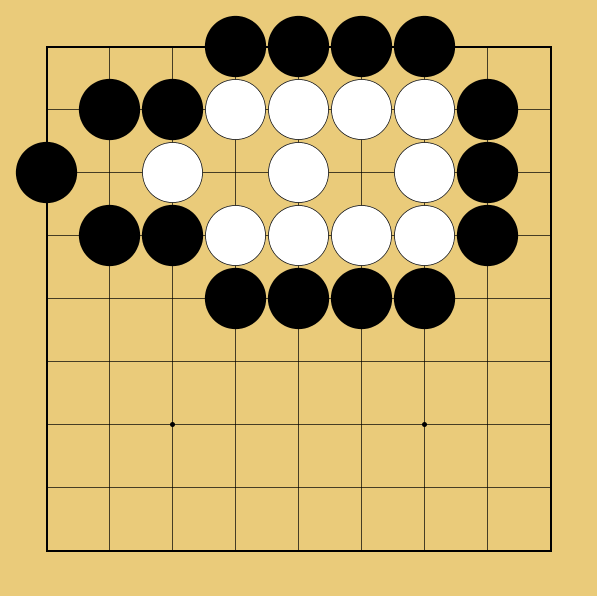
練習問題です。
この白は生きていますか?
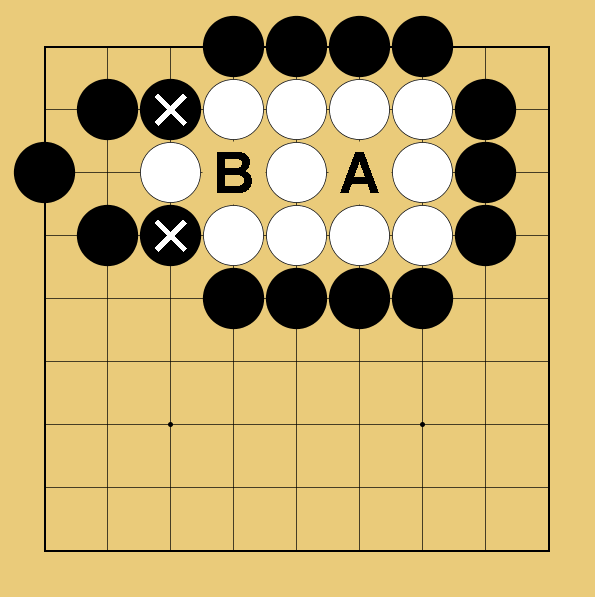
【解答】Aしか眼がない状態で死んでいます。
Bは黒×によって「欠け眼」ですね。
大丈夫そうでしょうか。
死活の判断練習④
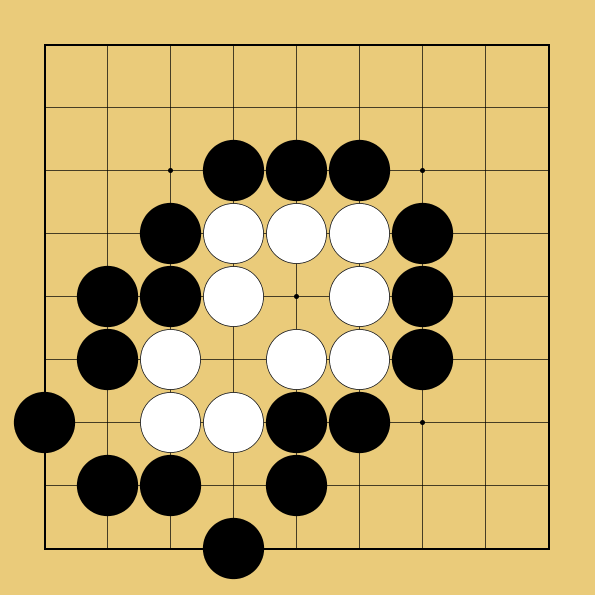
この図の白はどうでしょうか?
「生き」か「死に」か…
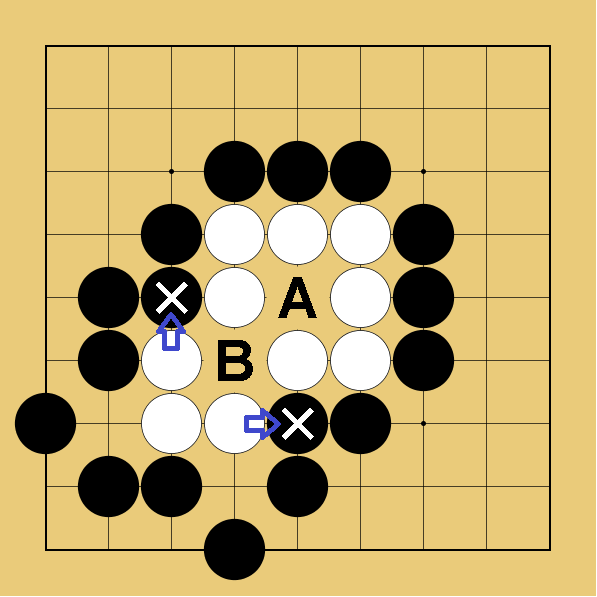
【解答】この白も、Bの場所が「欠け眼」です。
白の道を黒×がジャマしています。
白はAにしか眼がなく、「一眼で死に」ということになります。
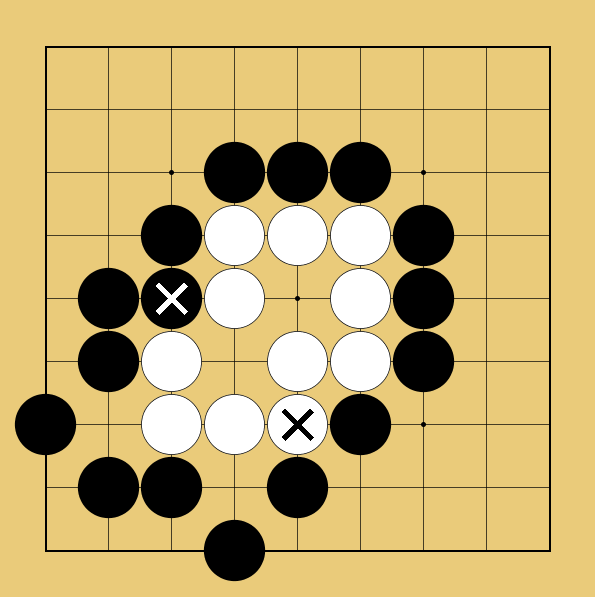
例えば、片方の×が白石でしたら、
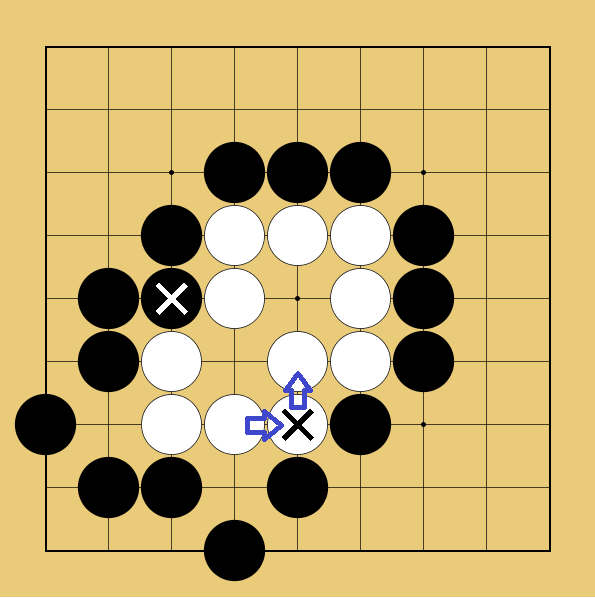
こういう感じで、縦横の道でつながっているので白の眼になります。
この図は、二眼あって生きているのですね。
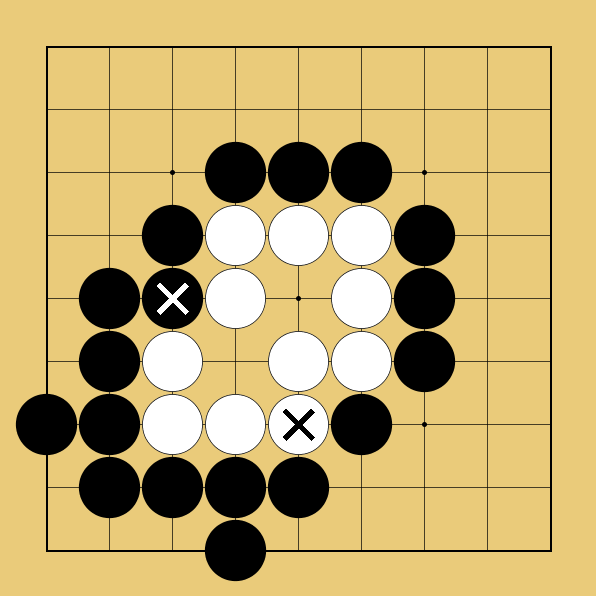
黒にびっしりと囲まれても、白がアタリになることはありません。
白×のおかげですね。
どうでしょうか。
「欠け眼」についてだんだん分かってきましたか?
理論が分かってきたら、あとは練習問題をたくさん解いて目を慣らすだけです。
次は「中手(なかで)」というものについて見ていきましょう。
※囲碁入門ではどんなことを学ぶのか?という今後の全体像については下のまとめ記事をご参考ください。